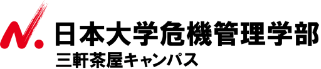4つの履修モデル
災害マネジメント領域
災害マネジメント領域で育成を目指す人材像
- 自然災害や大規模事故等の災害に対する対応と備えについて多角的な観点から考え、具体的解決策を導き出すための素養を身につけた人材。
- 災害発生時、自らの能力とあらゆる資源を駆使して自らとその家族の身体、生命、財産を守り、被害からの迅速な回復に取り組む意欲を持つ人材。
- 自らの暮らす地域及び自らの所属する組織を災害から守り、被害から迅速に回復するために必要な取り組みについて、日頃、関係者とともに協力しながら試行錯誤しそれを実践することができる人材。
※1 科目名の前に付記されている記号で、◎は必修科目、◯は選択必修科目を表す。
※2 卒業要件に必要となる最低限の修得単位数を前提とした履修モデルである。
総合教育科目
※A:「別表 総合科目一覧」からいずれか選択
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎自主創造の基礎(前) ◎アカデミック・スキルズ(後) ◎コンピュータ・情報リテラシー(前/後) ◎スポーツ講義・スポーツ実技1(前/後) ◎英語I~Ⅳ(前・後、各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A 総合科目1・2(前・後)※A |
○英語V~Ⅶ(前・後、各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 総合科目1・2(前・後)※A | 総合科目1・2(前・後)※A |
※A 別表 総合科目一覧
生活と法、哲学、論理学、倫理学、宗教学、歴史学、近代史、文学、教育学、社会学、政治学、経済学、地理学、心理学、文化人類学、数学、統計学、文章表現、科学技術史、地球科学、健康の科学、教養特殊講義、救急処置法、日本を考える、スポーツ実技2・3
専門基幹科目
※B:行政キャリア推奨、※C:企業キャリア推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎危機管理学概論(前) ◎法学概論(前) ◎行政リスクガバナンス(後) ◎企業リスクガバナンス(後) ◎リスクマネジメント(前) ◎リスクコミュニケーション(後) ○インテリジェンス(前) ○セキュリティ(後) ○情報技術と社会(後)※C ○憲法と人権(後) ○民事法Ⅰ(後)※C |
○ロジスティクス(前) ○ヒューマンエラー(後) ○立憲主義と統治(前)※B ○行政法と行政過程I(前)※B ○行政法と行政過程Ⅱ(後)※B ○犯罪と法Ⅰ(前) ○民事法Ⅱ(前)※C ○民事法Ⅲ(後)※C ○企業取引と法(前)※C ○企業組織と法(後)※C 行政学(前)※B 経営学(前)※C 会計学(後)※C 社会心理学(前) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| ○企業統治と法(前)※C ○リスクファイナンスI(前)※C ○リスクファイナンスⅡ(後)※C ○民事手続と法(前)※C 経済法(前) 外国法(後) 日本思想論(後) 国際自然·環境論(後) 比較宗教·文化論(後) |
専門展開科目
※D:専攻1領域から〇の選択必修2単位を含む16単位を履修、領域の選択必修は2科目とることを推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| 共通学修 ボランティア論(前) 国際関係論(後) |
共通学修 社会調査論(前) 感染症対策論(後) 専門英語コミュニケーション1·2(前·後) 海外実地研修(集中) キャリアデザインI(後) 災害マネジメント領域 ※D ○災害対策論(前) ○自然災害論(前) 災害情報論(前) 地域防災論(後) 大規模事故論(後) 消防救急論(後) 統合学修 ◎基礎ゼミ(前) ◎ゼミナールI(後) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 共通学修 危機管理特殊講義1~6(前·後) 危機管理実践研究1(集中) 観光リスクマネジメント(後) 事業継続論(BCP·BCM)(後) 専門英語プレゼンテーション1·2(前·後) キャリアデザインⅡ(集中) 災害マネジメント領域 ※D 災害と法(前) 災害史(前) 原子力と安全(前) 事故責任法制(後) 復旧·復興論(後) 統合学修 ◎ゼミナールⅡ·Ⅲ(前·後) |
共通学修 国際地域研究1·2(前·後) 統合学修 ◎ゼミナールⅣ·V(前·後) |
履修モデル図
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○社会安全政策論(前) 犯罪心理学(前) 警察行政(後) 国民保護(後) |
テロリズム論(後) インフラセキュリティ(後) 被害者学(後) |
|
| 他領域科目 | グローバルセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 情報セキュリティ領域 領域から最低 4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○国際法(前) ○国際政治学(前) 防衛法制(後) 安全保障論2(後) |
防衛政策(前) 平和構築論(前) 国際化と国境管理(後) |
|
| 他領域科目 | パブリックセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 情報セキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○情報法(前) ○情報倫理(前) メディアコミュニケーション論(前) 情報管理論(前) プライバシーと法(後) ジャーナリズム論(後) |
企業広報論(前) | |
| 他領域科目 | パブリックセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 グローバルセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
パブリックセキュリティ領域
パブリックセキュリティ領域で育成を目指す人材像
〔具体例〕行政キャリアでは、警察官をはじめとする公安職系の公務員等として活躍できる人材。企業キャリアでは、企業·団体の危機管理業務を担当できる人材。
※1 科目名の前に付記されている記号で、◎は必修科目、◯は選択必修科目を表す。
※2 卒業要件に必要となる最低限の修得単位数を前提とした履修モデルである。
総合教育科目
※A:「別表 総合科目一覧」からいずれか選択
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎自主創造の基礎(前) ◎アカデミック・スキルズ(後) ◎コンピュータ・情報リテラシー(前/後) ◎スポーツ講義・スポーツ実技1(前/後) ○英語I~Ⅳ(前・後,各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A 総合科目1・2(前・後)※A |
○英語V~Ⅷ(前・後、各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 総合科目1・2(前・後)※A | 総合科目1・2(前・後)※A |
※A 別表 総合科目一覧
生活と法、哲学、論理学、倫理学、宗教学、歴史学、近代史、文学、教育学、社会学、政治学、経済学、地理学、心理学、文化人類学、数学、統計学、文章表現、科学技術史、地球科学、健康の科学、教養特殊講義、救急処置法、日本を考える、スポーツ実技2・3
専門基幹科目
※B:行政キャリア推奨、※C:企業キャリア推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎危機管理学概論(前) ◎法学概論(前) ◎行政リスクガバナンス(後) ◎企業リスクガバナンス(後) ◎リスクマネジメント(前) ◎リスクコミュニケーション(後) ○インテリジェンス(前) ○セキュリティ(後) ○情報技術と社会(後)※C ○憲法と人権(後) ○民事法I(後)※C |
○ロジスティクス(前) ○ヒューマンエラー(後) ○立憲主義と統治(前)※B ○行政法と行政過程I(前)※B ○行政法と行政過程Ⅱ(後)※B ○犯罪と法Ⅰ(前) ○民事法Ⅱ(前)※C ○民事法Ⅲ(後)※C ○企業取引と法(前)※C ○企業組織と法(後)※C 行政学(前)※B 経営学(前)※C 会計学(後)※C 社会心理学(前) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| ○企業統治と法(前)※C ○リスクファイナンスI(前)※C ○リスクファイナンスⅡ(後)※C ○民事手続と法(前)※C 経済法(前) 外国法(後) 日本思想論(後) 国際自然·環境論(後) 比較宗教·文化論(後) |
専門展開科目
※D:専攻1領域から〇の選択必修2単位を含む16単位を履修、領域の選択必修は2科目とることを推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| 共通学修 ボランティア論(前) 国際関係論(後) |
共通学修 社会調査論(前) 感染症対策論(後) 専門英語コミュニケーション1·2(前·後) 海外実地研修(集中) キャリアデザインI(後) パブリックセキュリティ領域 ※ D ○社会安全政策論(前) ○刑事司法手続I(前) 犯罪心理学(前) 警察行政(後) 犯罪と法Ⅱ(後) 国民保護(後) 刑事司法手続Ⅱ(後) インテリジェンスコミュニティ(後) 統合学修 ◎基礎ゼミ(前) ◎ゼミナールI(後) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 共通学修 危機管理特殊講義1~6(前・後) 危機管理実践研究2(集中) 観光リスクマネジメント(後) 事業継続論(BCP・BCM)(後) 専門英語プレゼンテーション1・2(前・後) キャリアデザインⅡ(集中) パブリックセキュリティ領域 ※D 犯罪と捜査(前) 法医学(前) テロリズム論(後) インフラセキュリティ(後) 少年法(後) 被害者学(後) 経済刑法(後) 統合学修 ◎ゼミナールⅡ・Ⅲ(前·後) |
共通学修 国際地域研究1・2(前·後) 統合学修 ◎ゼミナールⅣ・V(前·後) |
履修モデル
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○災害対策論(前) 地域防災論(後) 消防救急論(後) 大規模事故論(後) |
災害と法(前) 原子力と安全(前) 事故責任法制(後) |
|
| 他領域科目 | グローバルセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 情報セキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○国際法(前) 安全保障論1(前) 防衛法制(後) 国際人権·人道法(後) |
防衛政策(前) 平和構築論(前) 国際化と国境管理(後) |
|
| 他領域科目 | 災害マネジメント領域 領域から最低4単位を選択 情報セキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○情報法(前) ○情報倫理(前) メディアコミュニケーション論(前) サイパーセキュリティ論(後) プライバシーと法(後) |
デジタル·フォレンジック(前) 知財セキュリティ論(後) |
|
| 他領域科目 | 災害マネジメント領域 領域から最低4単位を選択 グローバルセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
グローバルセキュリティ領域
グローバルセキュリティ領域で育成を目指す人材像
- ものごとを多面的、横断的、立体的にとらえ、歴史的・地理的背景なども念頭に置きつつ、的確に問題を認識し、関心対象を見出す能力を有する人材。
- 日本がおかれた状況を客観的に見据えつつ、広い視野および国際的な視点を有する人材。
- 正しい日本語の表現能力を前提に、外国語能力(必修科目の英語のみならず、できれば、隣国の言語である中国語または韓国語)を有し、自分と異なる文化的背景・価値観を有する人々を理解するグローバルな感覚を有する人材。
- 膨大な情報の中から、必要な情報(インテリジェンス)を入手・抽出し、利用することができる人材。
※1 科目名の前に付記されている記号で、◎は必修科目、◯は選択必修科目を表す。
※2 卒業要件に必要となる最低限の修得単位数を前提とした履修モデルである。
総合教育科目
※A:「別表 総合科目一覧」からいずれか選択
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎自主創造の基礎(前) ◎アカデミック・スキルズ(後) ◎コンピュータ・情報リテラシー(前/後) ◎スポーツ講義・スポーツ実技1(前/後) ○英語I~Ⅳ(前・後、各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A 総合科目1・2(前・後)※A |
○英語V~Ⅷ(前・後、各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 総合科目1・2(前・後)※A | 総合科目1・2(前・後)※A |
※A 別表 総合科目一覧
生活と法、哲学、論理学、倫理学、宗教学、歴史学、近代史、文学、教育学、社会学、政治学、経済学、地理学、心理学、文化人類学、数学、統計学、文章表現、科学技術史、地球科学、健康の科学、教養特殊講義、救急処置法、日本を考える、スポーツ実技2・3
専門基幹科目
※B:行政キャリア推奨、※C:企業キャリア推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎危機管理学概論(前) ◎法学概論(前) ◎行政リスクガバナンス(後) ◎企業リスクガバナンス(後) ◎リスクマネジメント(前) ◎リスクコミュニケーション(後) ○インテリジェンス(前) ○セキュリティ(後) ○情報技術と社会(後)※C ○憲法と人権(後) ○民事法Ⅰ(後)※C |
○ロジスティクス(前) ○ヒューマンエラー(後) ○立憲主義と統治(前)※B ○行政法と行政過程I(前)※B ○行政法と行政過程Ⅱ(後)※B ○犯罪と法Ⅰ(前) ○民事法Ⅱ(前)※C ○民事法Ⅲ(後)※C ○企業取引と法(前)※C ○企業組織と法(後)※C 行政学(前)※B 経営学(前)※C 会計学(後)※C 社会心理学(前) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| ○企業統治と法(前)※C ○リスクファイナンスI(前)※C ○リスクファイナンスⅡ(後)※C ○民事手続と法(前)※C 経済法(前) 外国法(後) 日本思想論(後) 国際自然・環境論(後) 比較宗教・文化論(後) |
専門展開科目
※D:専攻1領域から〇の選択必修2単位を含む16単位を履修、領域の選択必修は2科目とることを推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| 共通学修 ボランティア論(前) 国際関係論(後) |
共通学修 社会調査論(前) 感染症対策論(後) 専門英語コミュニケーション1・2(前・後) 海外実地研修(集中) キャリア・デザインI(後) グローバルセキュリティ領域 ※D ○国際法(前) ○国際政治学(前) 安全保障論1(前) 防衛法制(後) 安全保障論2(後) 国際人権・人道法(後) ストラテジー(後) 外交史(後) 統合学修 ◎基礎ゼミ(前) ◎ゼミナールI(後) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 共通学修 危機管理特殊講義1~6(前・後) 危機管理実践研究3(集中) 観光リスクマネジメント(後) 事業継続論(BCP・BCM)(後) 専門英語プレゼンテーション1·2(前·後) キャリア・デザインⅡ(集中) グローバルセキュリティ領域 ※D 防衛政策(前) 平和構築論(前) 国際化と国境管理(後) 統合学修 ◎ゼミナールⅡ·Ⅲ(前·後) |
共通学修 国際地域研究1・2(前・後) 統合学修 ◎ゼミナールⅣ・V(前・後) |
履修モデル
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | 〇災害対策論 (前) 〇自然災害論(前) 大規模事故論(後) |
災害と法(前) 原子力と安全(前) 事故責任法制(後) 復旧・復興論(後) |
|
| 他領域科目 | パブリックセキュリティ領域 領域から最低4 単位を選択 情報セキュリティ領域 領域から最低4 単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○社会安全政策論(前) 犯罪心理学(前) 警察行政(後) 国民保護(後) インテリジェンスコミュニティ(後) |
テロリズム論(後) インフラセキュリティ(後) |
|
| 他領域科目 | 災害マネジメント領域 領域から最低4単位を選択 情報セキュリティ領域 領域から最低 4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○情報法(前) ○情報倫理(前) 情報管理論(前) メディアコミュニケーション論(前) サイバーセキュリティ論(後) プライバシーと法(後) |
知財セキュリティ論(後) | |
| 他領域科目 | 災害マネジメント領域 領域から最低4単位を選択 パブリックセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
情報セキュリティ領域
情報セキュリティ領域で育成を目指す人材像
- 情報セキュリティに関する問題解決には多くの場合広い知見が求められるため、情報処理の一般的な知識に加えて、サイパー攻撃の手口やシステム管理等関連する情報技術、更に情報法、刑法等の法律の知識、情報管理に関する諸制度等に習熟した人材。
- 技術の進化が絶え間なく変化して社会的な制度も流動的な状況にあるため、既取得の知識や技術に囚われることなく、最新の技術要素を積極的に修得する意欲を持つ人材。
- 複数の因果関係が絡み合う情報セキュリティの問題を、技術的な見地に偏重することなく、問題要素の関係を読み解き、法律知識、技術的な見識、論理的な考察、高い倫理観を以って社会的合意を形成してステークホルダーに利益をもたらす合理的な解法を提案できる人材。
※1 科目名の前に付記されている記号で、◎は必修科目、◯は選択必修科目を表す。
※2 卒業要件に必要となる最低限の修得単位数を前提とした履修モデルである。
総合教育科目
※A:「別表 総合科目一覧」からいずれか選択
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎自主創造の基礎(前) ◎アカデミック・スキルズ(後) ◎コンピュータ・情報リテラシー(前/後) ◎スポーツ講義・スポーツ実技1(前/後) ○英語I~Ⅳ(前・後、各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A 総合科目1・2(前・後)※A |
○英語V~Ⅷ(前・後、各週2回) 総合科目1・2(前・後)※A |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 総合科目1・2(前・後)※A | 総合科目1・2(前・後)※A |
※A 別表 総合科目一覧
生活と法、哲学、論理学、倫理学、宗教学、歴史学、近代史、文学、教育学、社会学、政治学、経済学、地理学、心理学、文化人類学、数学、統計学、文章表現、科学技術史、地球科学、健康の科学、教養特殊講義、救急処置法、日本を考える、スポーツ実技2・3
専門基幹科目
※B:行政キャリア推奨、※C:企業キャリア推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| ◎危機管理学概論(前) ◎法学概論(前) ◎行政リスクガバナンス(後) ◎企業リスクガバナンス(後) ◎リスクマネジメント(前) ◎リスクコミュニケーション(後) ○インテリジェンス(前) ○セキュリティ(後) ○情報技術と社会(後)※C ○憲法と人権(後) ○民事法I(後)※C |
○ロジスティクス(前) ○ヒューマンエラー(後) ○立憲主義と統治(前)※B ○行政法と行政過程I(前)※B ○行政法と行政過程Ⅱ(後)※B ○犯罪と法Ⅰ(前) ○民事法Ⅱ(前)※C ○民事法Ⅲ(後)※C ○企業取引と法(前)※C ○企業組織と法(後)※C 行政学(前)※B 経営学(前)※C 会計学(後)※C 社会心理学(前) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| ○企業統治と法(前)※C ○リスクファイナンスI(前)※C ○リスクファイナンスⅡ(後)※C ○民事手続と法(前)※C 経済法(前) 外国法(後) 日本思想論(後) 国際自然・環境論(後) 比較宗教・文化論(後) |
専門展開科目
※D:専攻1領域から〇の選択必修2単位を含む16単位を履修、領域の選択必修は2科目とることを推奨
| 1年 | 2年 |
|---|---|
| 共通学修 ボランティア論(前) 国際関係論(後) |
共通学修 社会調査論(前) 感染症対策論(後) 専門英語コミュニケーション1·2(前·後) 海外実地研修(集中) キャリアデザインI(後) 情報セキュリティ領域 ※D ○情報法(前) ○情報倫理(前) 情報管理論(前) 情報技術(前) メディアコミュニケーション論(前) ジャーナリズム論(後) サイバーセキュリティ論(後) プライバシーと法(後) 統合学修 ◎基礎ゼミ(前) ◎ゼミナールI(後) |
| 3年 | 4年 |
|---|---|
| 共通学修 危機管理特殊講義1~6(前·後) 危機管理実践研究4(集中) 観光リスクマネジメント(後) 事業継続論(BCP·BCM)(後) 専門英語プレゼンテーション1·2(前·後) キャリアデザインⅡ(集中) 情報セキュリティ領域 ※D デジタル·フォレンジック(前) 企業広報論(前) 知財セキュリティ論(後) 統合学修 ○ゼミナールⅡ·Ⅲ(前·後) |
共通学修 国際地域研究1・2(前·後) 統合学修 ◎ゼミナールⅣ・V(前·後) |
履修モデル
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○災害対策論(前) ○自然災害論(前) 災害情報論(前) 大規模事故論(後) 地域防災論(後) |
災害と法(前) 復旧·復興論(後) |
|
| 他領域科目 | パブリックセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 グローバルセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | 〇社会安全政策論(前) 警察行政(後) 国民保護(後) インテリジェンスコミュニティ(後) 犯罪と法Ⅱ(後) |
テロリズム論(後) インフラセキュリティ(後) |
|
| 他領域科目 | 災害マネジメント領域 領域から最低 4単位を選択 グローバルセキュリティ領域 領域から最低 4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択
| 2年 | 3年 | 4年 | |
|---|---|---|---|
| 副専攻科目 | ○国際法(前) ○国際政治学(前) 安全保障論2(後) ストラテジー(後) 外交史(後) |
防衛政策(前) 国際化と国境管理(後) |
|
| 他領域科目 | 災害マネジメント領域 領域から最低4単位を選択 パブリックセキュリティ領域 領域から最低4単位を選択 |
||
※ 副専攻の領域科目から10単位を選択